2025年7月20日(日)に、ピアニスト、ラフィ・べサリアンのリサイタルが大阪で開催されます。
今回のリサイタルでは、ラフマニノフ、プロコフィエフ、ラヴェルと多彩なプログラムで、正統ロシアン・ピアニズムを受け継ぐベサリアン氏の魅力を楽しめそうです。
そこで今回は、そんなプログラムの魅力や、ご自身の音楽との向き合い方などについて、べサリアン氏にたっぷりお話を伺いました。
ロシアン・ピアニズムとの出会いと、音で結ぶ聴衆との対話

べサリアン氏にこれまでの音楽家人生を振り返っていただくと、自身のピアニスト、また音楽家として最も大きな影響を与えたのは、今回のリサイタルでも演奏されるラフマニノフだと言います。
「私が生まれたとき、ラフマニノフはすでに亡くなっていましたが、彼の音楽はまだ生きていますよね。
私が幼い頃、エミール・ギレリスのコンサートをテレビで見ました。全曲ラフマニノフのプログラムでした。
その時に、有名な嬰ハ短調の前奏曲を聞いて、すぐにラフマニノフと壮大なロシアン・ピアニズムの世界に飲み込まれました。
そのロシアン・ピアニズム系統に代表されるピアニストのギレリス、多様なエネルギーを持ち色彩豊かなピアニストであったホロヴィッツ、そしてホロヴィッツの愛弟子であり、私の恩師でもある、華やかで非常に表現力豊かなピアニストであるバイロン・ジャニス。
この3人に、音楽的にも楽器へのアプローチも非常に影響を受けています。」
その上で、ピアニストとして演奏していく中で常に大切にしていることは、聴衆との《真のコミュニケーション》だと語ります。
「近日、世界各国で若手からベテランまで本当に多くの素晴らしいピアニストがいます。皆さんとても美しく、テクニック的にも音楽的にも卓越した演奏をされています。
もちろん私もそういった事における高いクオリティを目指して演奏会へ挑みますが、それよりもさらに私が大切にしている事はオーディエンスとの真のコミュニケーションです。私の演奏する音楽を通して、それにまつわる意味を伝えたいのです。
また、私は音楽にはとても強力な癒しの力があると感じているので、演奏によって湧き出る感情、ピアノの音そのもの、または音の振動などを通じて、聴衆に何かを持ち帰ってほしいと思っています。
それは何かわくわくとした気持ちだったり、幸福感かもしれないし、私の演奏によって聴いた人ひとりひとりに語りかけ、感じさせる独特なものであってほしい、というのが私の志す演奏です。」
ラフマニノフ、ラヴェル、プロコフィエフ——異なる声が交差する舞台
今回のリサイタルでは、ラフマニノフ、プロコフィエフ、ラヴェルと、いずれも個性の強い作曲家たちの作品を取り上げています。どのようなテーマや意図で選曲されたのかについて伺いました。
「おっしゃる通り!今回演奏する非常に個性の強い3人の作曲家達は、その時代の優秀なピアニスト達でもありました。
ですが、それぞれ全く違った個性やアプローチをします。その《違いのコントラスト》と、そこにまつわる《ドラマ》が、今回のリサイタルのテーマです。
まず、ラフマニノフ『コレルリの主題による変奏曲』は、ラフマニノフが作曲した最後のソロ・ピアノ曲ですが、特有のロマン派後期のものではなく、ネオ・バロックといえるような楽曲で、オープニングでの内に秘めた感情をもつシンプルなテーマ、その時期のラフマニノフの心情を映し出すような憂鬱と諦めの様なもの悲しさ、彼の歩んだ波乱に満ちた人生からラフマニノフのパーソナルなドラマを奏でたいです。
また、ヴァルトゥオーゾ的で管弦楽的なラヴェル『ラ・ヴァルス』は、ヴィエンナ・ワルツが反発的また破壊的となりカオスのような、荒れ狂う様になっていくドラマを。
そして、この2曲の間に挟んだ美しいアルメニアの楽曲であるコミタス『ガルーナ』、ハチャトゥリアン『仮面舞踏会よりワルツ』は、『ラ・ヴァルス』へのパーフェクトな橋渡しとなり、プロコフィエフ『ソナタ No.7』は人間の争いや対立、スターリン政権に対するプロコフィエフ自身のドラマともいえる内面的な葛藤を描いた楽曲で、今の時代に及んでもこの曲の持つ音魂は私たちの心に重く響くものがあります。」
ラヴェル『ラ・ヴァルス』はオーケストラ作品としても有名ですが、ピアノ版ならではの魅力や難しさはどのように感じているのでしょうか。
「まず、ラヴェル自身がピアノソロに編曲しましたが、元々オーケストラのためにかかれた曲ですので、最も重要であり、また難しさであるのは《オーケストラのように》という所でしょうね。
ソロ・ピアノでありながらオーケストラかのように、数々の楽器のような音色とスケールをもって弾く。それを目指すと、テクニック的にもどんどん難しさが増してきます。
そのため、私は過去に何度か自分で、自分の楽譜パーツの編集をしています。そうでなくては弾けない楽器のパーツがありますからね。そうすることによって、オーケストラとしてのクオリティを保てるように工夫する必要がありました。
しかし、これら全ての挑戦が実際に実現し調合された時、私のたった二つの手の内にオーケストラがあるかのような素晴らしい感覚を実現できるんです。
たった一台のピアノでオーケストラを指揮するような演奏ができますし、二つの手であるからこそもっと自由自在に音楽を操ることができます。」
最後に、べサリアン氏の演奏活動の中で、特に力を入れていることや、今後考えている取り組みなどについて伺いました。
「教育者としてもパフォーマーとしても共通して取り組んでいることは、様々な作曲家、古いもの、新しいもの含めて常に多様な楽曲を探ることです。
膨大な鍵盤楽曲のレパートリーの中から、全ての演奏をするというのは不可能かもしれませんが、常に新しいレパートリーを学ぼうと意識しています。
そしてもちろん、ソビエト時代における伝統的なロシアン・ピアニズムに育まれた私は、文字通りその世界から来た《最後のジェネレーション》と呼ばれる世代になります。
そのため、ロシアの作曲家の曲を通してロシアン・スクールの音楽的、身体的なピアノへのアプローチの仕方など大学での授業、レクチャーやレッスンをとおしてその伝統を継承し、次世代に受け継いでもらうための活動に力を注いでいます。
また、ロシアやアルメニアの作曲家による楽曲のレコーディングの出版も含め、これまであまり知られていなかったアルメニアの作曲家、エドワード・バグダサリアンによる『24の前奏曲』の初版編集をし、新版を Muse Pressより出版、また現在、エドワード・アブラミアン作曲の『24の前奏曲』の出版に向けて作業中です。」
公演情報
※本公演は終了しました。
ラフィ・ベサリアン ピアノリサイタル

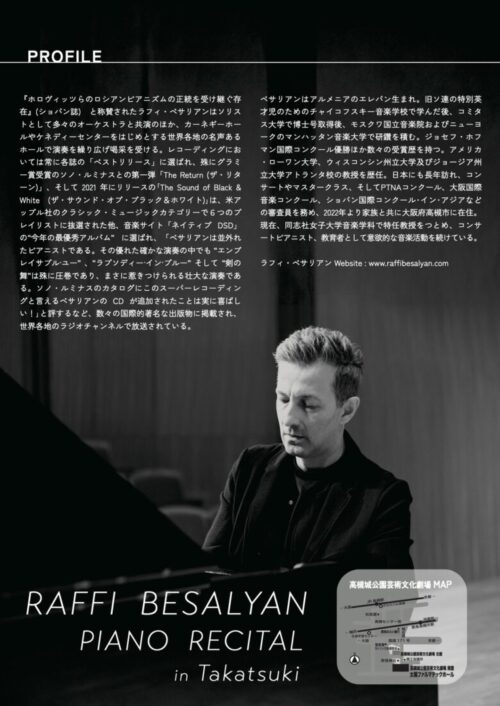
◆日時:2025年7月20日(日) 14:00開演
◆会場:高槻城公園芸術文化劇場・太陽ファルマテックホール
◆プログラム:
・ラフマニノフ:コレルリの主題による変奏曲
・プロコフィエフ:ソナタ No.7 作品83
・ラヴェル:ラ·ヴァルス 他





